事業承継にはさまざまな手法がありますが、経営者の高齢化に伴う後継者問題の解決策としてや企業の価値を維持するためなどにM&Aの手法を用いた事業承継型M&Aを利用する方法が注目されています。
事業承継やM&Aは、一般的に企業が何度も行うことではないので、実際に仕組みが難しく、何から手をつけて良いのか分からないという方も多いでしょう。
ここでは、そのような方のために事業承継型M&Aの仕組みやメリット・デメリット、他にも抑えておきたいポイントについて解説します。
Contents
日本国内が抱える事業承継問題の状況
日本の中小企業の間では、企業の「後継者問題」が過去より問題視されてきました。
高齢化社会に伴い経営者の高齢化も深刻な状態となっており、跡取りがいなくて会社を存続させられないケースや、会社を託すことができる後継者がいない為に、会社を存続できないなど悩ましい状況が続いていました。
しかし、2024年に帝国データバンクが「全国・全業種約 27 万社における 後継者動向」について調査した結果、7年連続で後継者不在率が下がるなど改善の傾向を見せているようです。
コロナ前の19年から比較しても13.1ポイント後継者不在率が低下するなど、大幅な改善傾向が見られています。
脱ファミリーの加速による事業承継への意識変化
前述の「全国・全業種約27万社における後継者動向」によると、従来一般的であった同族承継の割合が、2020年から2024年で、39.3%→32.2%と減少傾向を見せています。
一方で、企業の内部昇格は2020年から2024年では31.9%→36.4%に増加、同じくM&Aの数値は17.2%→20.5%に増加しています。
これは後継者としての候補が「同族」より「非同族」へとシフトしており、事業承継のあり方が脱ファミリー化の方向へと加速していることを意味します。
事業承継型M&Aは、脱ファミリー化を行う際の事業承継において、有効な選択肢のひとつとなります。
事業承継とM&Aについて

上記では事業承継を取り巻く環境を解説しましたが、実際のところ事業承継とM&Aに関して同じような意味と考えている方が多いかもしれません。
よく間違われるのは、事業承継は中小企業が利用する手法で、M&Aは大企業が利用する手法であるということです。
しかし、実際は全く異なります。
事業承継とは
事業承継とは、現経営者が会社の経営権を後継者に譲り渡すことを指します。
経営者が別の個人や企業に変わった後も、変更前と同様に円滑な経営が推進されるように、株式や経営資源などが引き継がれます。
事業承継の種類としては、親族内承継、親族外承継、M&Aがその中に含まれます。
M&Aとは
M&Aとは、「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の略で、2つ以上の企業が合併や買収をすること、ベースとなる企業が他の企業を買収すること、またはそれらを含む企業提携の総称のことを指します。
広義の意味でM&Aは、「合併」「買収」「合弁会社設立」「資本参加」の4つの手法を用いて行われます。
事業承継とM&Aの違い
M&Aは事業承継を行う際に選択するひとつの手法となっており、定義として事業承継の際に現経営者が後継者に事業を引き継ぐことを目的にしています。
それに対して、M&Aは事業が他の人の手に渡るという点では同じですが、企業同士が合併や買収することを目的としている点が異なります。
事業承継型M&Aとその仕組み
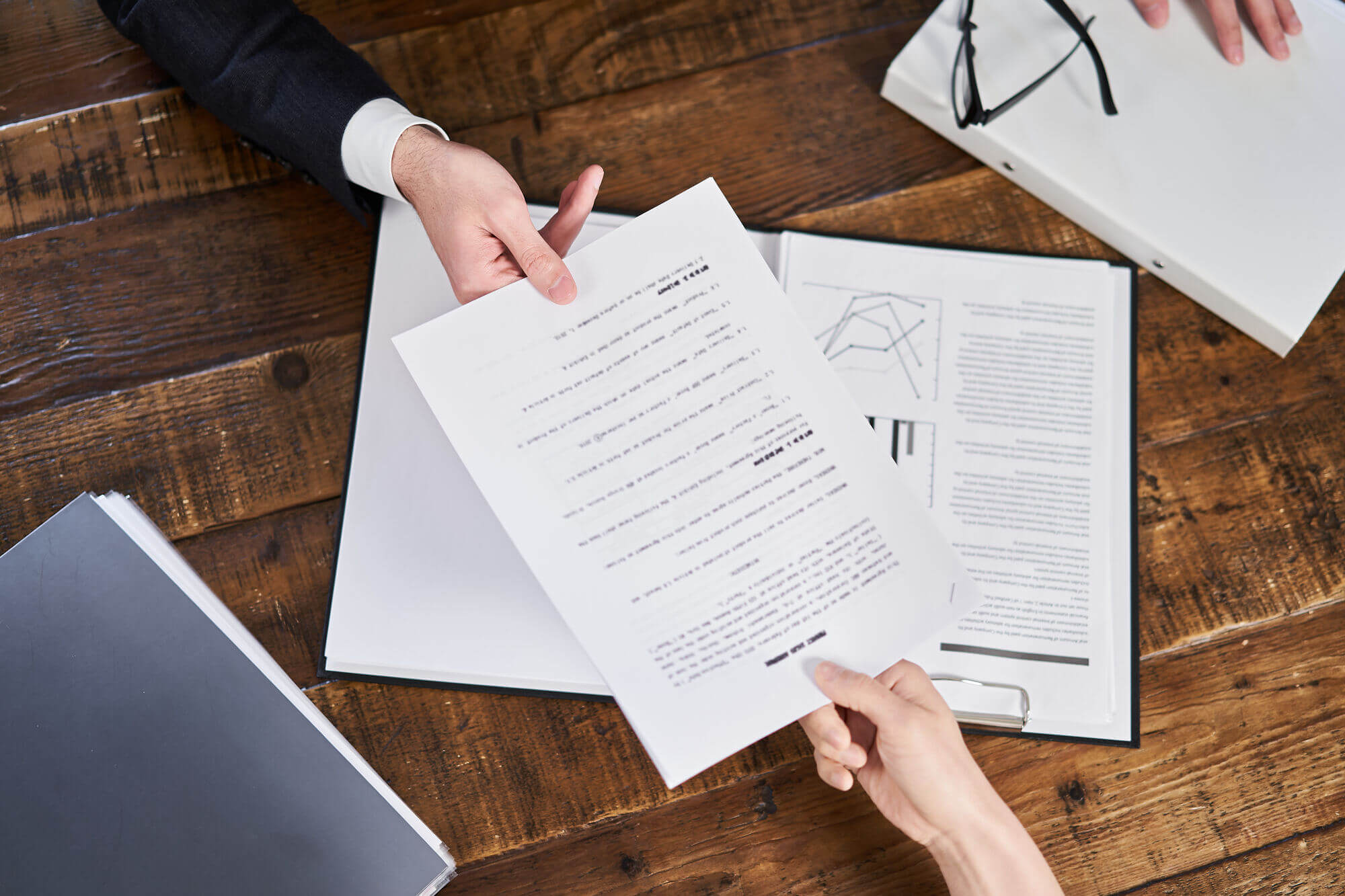
事業承継とM&Aの違いを確認しましたが、事業承継型M&Aとはどのような手法なのでしょうか。
事業承継型M&Aの主な目的
一般的な事業承継は、企業の競争力強化や成長戦略を主な目的として事業承継を行います。
それに対して、事業承継型M&Aでは、経営者が高齢などの理由により後継者がいない場合や、従業員に後継者として引退後の会社を任せられる人材がいない場合の問題を解決することを目的として行われます。
その他にも事業承継型M&Aの活用方法としては、以下のような例があります。
- 屋号の継続(会社名の継続を目的とする)
- 従業員の雇用を継続させたい
- 経済的な対価を最大化させたい
- 取引関係を継続させたい
条件や目的によっては、売り手と買い手とでは求めるビジョンが異なるので十分に検討する必要があります。
事業承継型M&Aの仕組み
M&Aは、事業承継を行う際のひとつの手段となるので、M&Aで事業承継を行うことを決めたら事業承継する目的を上記の中より明確に定める必要があります。
目的が明確になったら、M&Aの仲介業者に相談を行い、売り手と買い手を繋ぐためにマッチングをします。
マッチングで具体的な交渉相手が見つかった際には、事業調査を行い双方の利益を最大化することができているのか確認します。
買い手企業が見つかった後に、デューデリジェンス(企業調査)を行い経営状況や財務状況、法的問題がないかなど詳細を調査する過程を経て契約となります。
【合わせて読みたい記事】
事業承継型M&Aのメリット
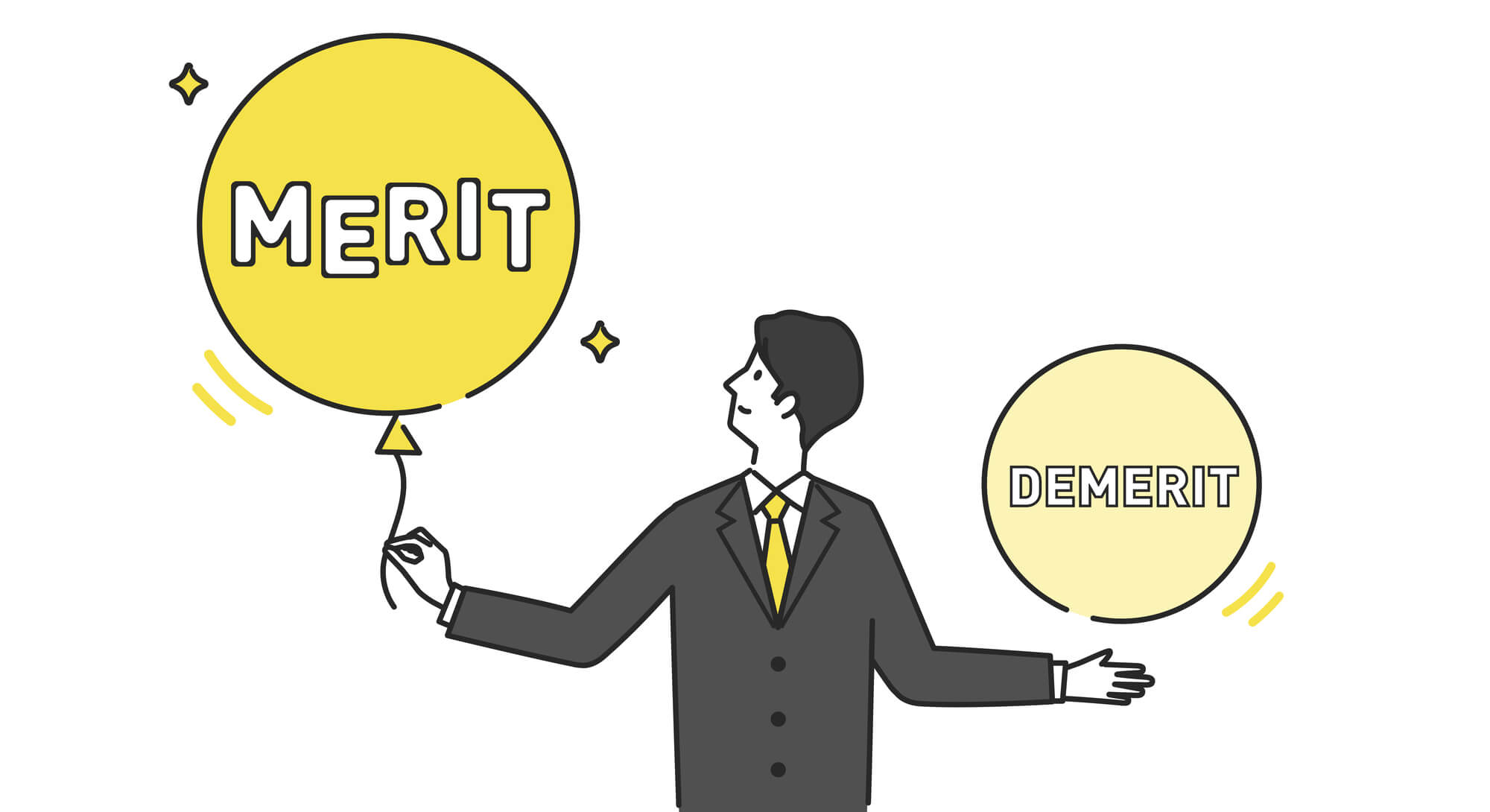
事業承継型M&Aには、以下のようなメリットがあります。
後継者がいない問題を解決できる
近年では、前述のように日本国内の中小企業の経営者が高齢化になりつつある傾向により、後継者不足が問題視されています。
事業承継型M&Aを利用することで、次の世代に企業を託すことができない場合による廃業の危機を回避することができます。
企業を継続させることにより雇用と取引先を維持できる
会社を清算した場合や、事業売却した際に従業員は職を失うことになります。
このようなケースにおいても、事業承継型M&Aを活用することで現在の従業員の雇用を維持しながら事業の承継が行えるメリットがあります。
雇用を維持したまま事業承継するので、業務のノウハウを保有したままの事業継続が可能となり、得意先との関係を良好のまま事業を継続できることになります。
創業者の利潤を確保できる
事業を廃業した際には、固定資産の処分や長年従事してくれた従業員に対しての退職金などの清算を行うことで、最終的に負債が残ることもあります。
事業承継型M&Aを活用すると、上記のように従業員の雇用は維持したままM&Aにより自社株を売却することで利益を得ることができます。
創業者は、事業承継型M&Aにて得た資金でセカンドライフを楽しむことや、新たな事業に向けての資金として将来を設計する資本としての蓄えを増やすことができます。
創業者が築いた事業を後世に残せる
事業承継型M&Aでは、基本的に事業を第三者に承継するので経営者が変わります。
時間をかけて築いた事業は第三者の手に渡ることになりますが、ご自身が構築した事業が買い手側の企業の力によりさらに拡大していく姿をみることができます。
特に買い手側の規模が大きい場合などは、事業間のシナジー効果により新たな市場へ大きく展開して規模拡大する可能性もあります。
個人での事業保証が無くなる
中小企業の経営者は、金融機関から資金を借りる場合など事業資金の調達のために個人で保証を背負うケースがあります。
個人保証のリスクがある為に、事業が親族や社内従業員へ承継される際の妨げになることもあります。
事業承継型M&Aを利用すると、譲渡する企業に個人保証の解除を前提とした承継を交渉することができます。
事業承継型M&Aのデメリット
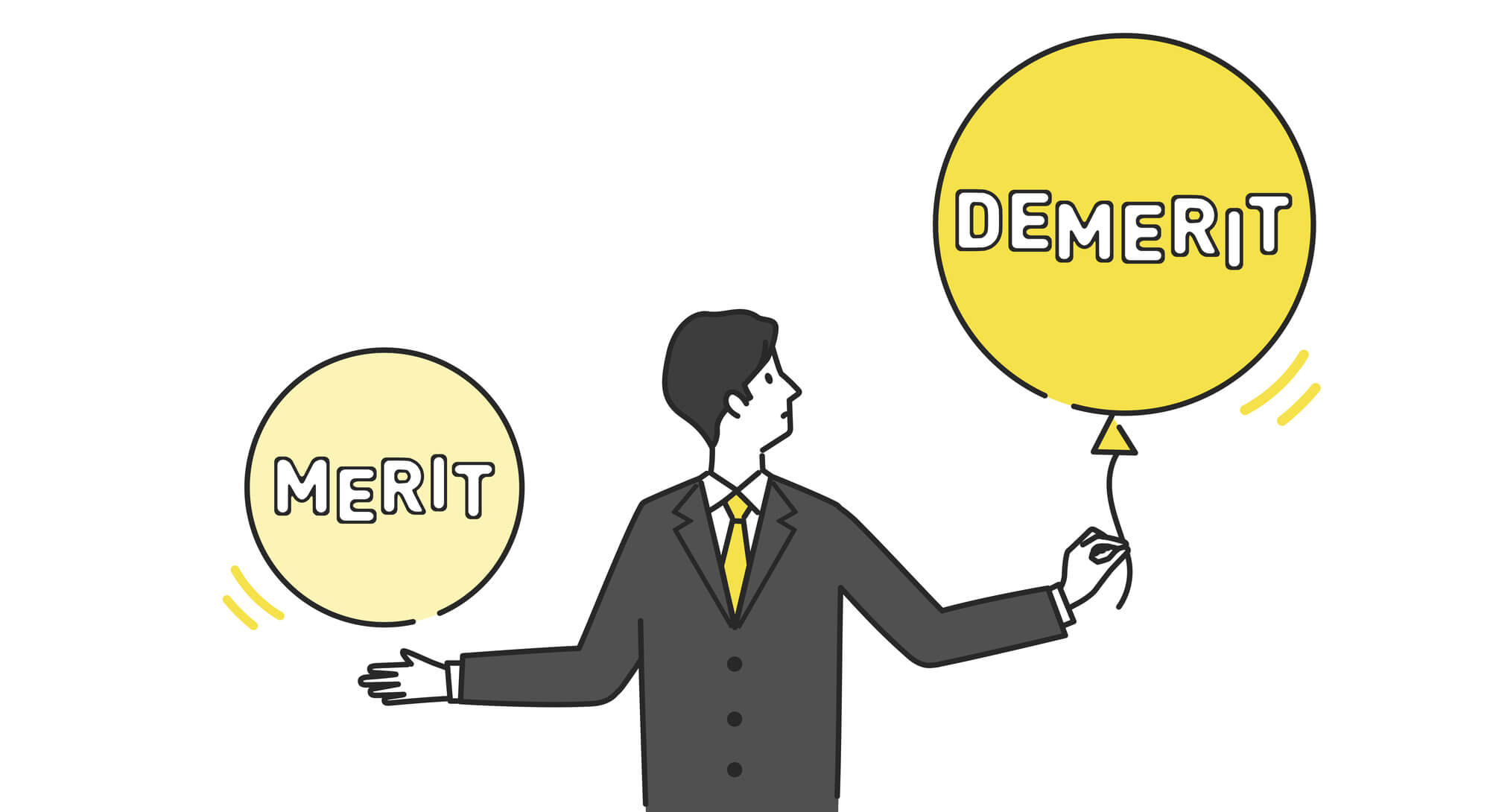
事業承継型M&Aには前述のようなメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。
買収先によっては経営方針や組織が大幅に変更になる
事業承継型M&Aでは、基本的に売却前に勤めている従業員も引き継がれます。
旧組織の方針を理解した経営者ばかりではないので、承継後に待遇などが変更になる可能性があります。
このような場合には、事前にM&A成立の条件に雇用形態や経営方針の維持を条件とした交渉を行う必要があります。
急激に経営方針を変えるなどした場合には、理解を得られずに離反する社員が出る可能性もあります。
新たな経営者が既存従業員や取引先から理解を得られない場合がある
事業承継型M&Aでは、経営者が変更するので新たな経営者と従業員との間で条件面など反発が生じることがあります。
また、経営方針の違いにより取引先から信頼を得られない場合もあり、その場合には一時的な取引停止や取引そのものが滞るケースなどもあります。
情報漏洩により経営に悪影響を及ぼすこともある
M&Aを検討しているということは、良いイメージばかりではありません。
後継者不足で事業承継型M&Aを活用しようと検討している場合でも、企業の外側から見ると業績が悪化しているから事業を譲渡しようと検討しているようにも見えかねます。
企業にマイナスイメージがつくと、M&Aが失敗する場合や、思ったような価格で売却できなくなる恐れがあるので注意が必要です。
必ずしもM&Aにて売却した際に利潤が確約されるわけではない
メリットで利潤が確保できると解説しましたが、必ずしも全てのケースで売却による利潤が確保できるわけではありません。
売却する際の金額は、売り手と買い手との間で交渉により決められます。
売却側の企業が自社の将来性を高く考えていない場合などは、企業の資産価値よりも安価な価格を提示されることがあります。
そのような場合には、結果的に収支がマイナスになる恐れがあるので注意が必要です。
事業承継型M&Aでは多くの時間と労力が必要になる
経営者が希望する条件での買い手が見つからない場合には、希望に沿った条件で売却できる相手を見つける必要があります。
希望通りの買い手がすぐに見つかることは稀なので、条件が合う相手探しには多くの時間を要します。
また、良い買い手が見つかった場合でも、事業承継型M&Aを行う際には事前に株主総会の決議などが必要になります。
事業承継型M&Aの場合には、債権債務移転手続きが必要になるので、通常より多くの時間と費用を要すことになります。
悪質なM&A仲介業者により不誠実な取引がなされる可能性
昨今話題になっている悪質なM&A仲介業者により本来得られるはずであった上述したメリットが教授されず不利益を被る可能性がある為、M&A仲介業者選びやセカンドオピニオン的な業者を間に入れる事が重要と言えます。
事業承継型M&Aを行う際のポイント

事業承継型M&Aを行う際には、円滑に事業承継をするために次のようなポイントに着目する必要があります。
事業承継するタイミングを見極める
事業承継型M&Aを活用する場合には、適切なタイミングで実施する必要があります。
一般的にM&Aでは、事業規模は大きくなればなる程、現経営者から新たな経営者への業務の引き継ぎに時間が掛かると言われます。
経営者が引退間近の状態では、引き継ぎへの期間が十分に用意できないばかりか、廃業直近の企業であるという印象を持たれて良い条件で交渉ができない場合もあります。
その為に、後継者探しという意味でもある程度早い段階で活発的に動ける状態の時に事業承継を検討して取り組む必要があります。
事業承継型M&Aに関する支援策を利用する
中小企業の間で、企業存続のための後継者問題が課題とされている中で、政府も事業承継型M&Aを後押ししており、事業承継を行う際に活用できる公的支援を各種用意しています。
主な例としては以下のようなものがあります。
- 事業承継、引継ぎ支援センター
- 事業承継、引継ぎ補助金
- 法人版事業承継税制
- 個人版事業承継税制
- 事業承継ファンド
- 日本政策金融公庫による融資
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継、引継ぎ支援センターは、全国47都道府県に公的相談窓口として設置されており、後継者不在に悩む中小企業や事業承継に向けた取組について悩みを抱える経営者に対して事業承継計画策定支援や、マッチング支援等を対応してもらうことができます。
国の事業として行っているので、無料で専門家の意見やアドバイスが聞けるのが特徴になります。
事業承継、引継ぎ補助金
事業承継M&Aを行った後には、先代経営者として「事業引き継ぎ等に係る費用」、後継者として「承継後の取組に掛かる費用」がそれぞれに発生します。
また承継時に伴い「承継後に伴う廃業に係る費用」なども発生します。
事業承継、引継ぎ補助金では、この3つの費用を補助します。
具体的な金額としては以下のようになります。
| 支援の枠組み | 補助率 | 補助額 |
|---|---|---|
| ①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組に係る費用の補助 | ||
| 経営革新枠*1 | 1/2・2/3 | ~600万円 |
| 1/2 | 600万円~800万円*2 | |
| ②経営資源引継ぎ時の士業専門家等の活用に係る費用の補助 | ||
| 専門家活用枠 | 1/2・2/3 | ~600万円 |
| ③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に伴う廃業費用等の補助 | ||
| 廃業・再チャレンジ枠*3 | 1/2・2/3 | ~150万円 |
*2一定の賃上げを実施する場合には、補助上限額が上乗せされる
*3経営革新枠または専門家活用枠と併用での利用が可能となる
経済産業省「事業承継・M&Aに関する主な支援策」参照
「事業引き継ぎ等に係る費用」では最大600万円〜800万円、「承継後の取組に掛かる費用」では最大600万円、「承継後に伴う廃業に係る費用」では最大150万円の補助が受けられます。
法人版事業承継税制
法人版事業承継税制とは、事業承継後に後継者が経営承継円滑化法の認定を受け、非上場会社の株式等を贈与又は相続等によって取得した場合に、非上場株式等に係る贈与税相続税の納税を猶予してもらえる制度になります。
特例承継計画の提出が必要な特例措置での納税猶予割合は100%、一般措置では贈与の場合は100%、相続の場合は80%などの猶予が設けられます。
個人版事業承継税制
個人版事業承継税制とは、事業承継の後継者が経営承継円滑化法の認定を受けて、特定事業用資産*を贈与・相続等で取得した場合に、10年間の特例措置として特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額を猶予できる制度になります。
*事業用の土地、建物、乳牛、果樹、機械器具備品等
事業承継ファンド
事業承継M&Aを活用して、新事業展開やグループ化等で経営基盤の強化を目指す中小企業が、中小機構のファンドによる資金提供を受けることができるシステムになります。
国の支援機関ということもあり、様々な支援メニューがあります。
日本政策金融公庫による融資
日本政策金融公庫とは、財務省が管轄する金融機関になります。
日本政策金融公庫では、中期的な事業承継を計画している企業や、後継者と共に事業承継計画を策定している方に融資を行っています。
融資期間は中長期的で、10年〜20年の期間内で融資を受けられます。
上記は支援の一部となります。
詳細は経済産業省の「事業承継・M&Aに関する主な支援策」にて解説があるので、具体的にお考えの方は確認してみてはいかがでしょうか。
事業承継ガイドラインに則り取り進める
事業承継を行う際には、中小企業庁が公式HPにて公開している「事業承継ガイドライン」に則って進めると計画的に進めることができます。
ガイドラインでは、事業承継の課題を明確にすると共に、事業承継に向けた準備の必要性の認識、経営状況・経営課題等の把握、事業承継に向けた経営改善、事業承継計画の策定、M&Aの工程の実施事業承継・M&Aの実行まで5つのステップで分かりやすく解説されているので利用すると良いでしょう。
事業承継やM&Aの専門家に相談する
事業承継やM&Aを行う際には、それぞれに多くの法律や複雑な手続きが絡んできます。
深い知識を持たないまま実施すると、事業承継したのに承継した企業が不祥事を発生させた際の責任を負わされるなどトラブルの原因になります。
事業承継型M&Aの知識を有して、的確なアドバイスを提供できる専門家や企業コンサルタントなどの力を借りると安心して取り組むことができます。
事業承継型M&Aを利用する際の注意点

事業承継型M&Aを利用する際には、事前に注意しておかなくてはトラブルの原因になることがあります。
事業承継を予定している企業の株主や役員との関係性
企業の株主や役員との間で、事業承継型M&Aを活用することの意思疎通が取れていないと大きな問題になる恐れがあります。
個人商店であれば特に問題視されませんが、中規模の会社になると社内において重要な役割を果たす方々との意思疎通不足があるとスムーズな交渉ができにくくなります。
また、社内の意思疎通が取れていないことが買い手側に伝わると、交渉そのものが頓挫する可能性もあります。
仲介業者や買手企業の意見に惑わされない
相手を尊重して交渉に挑む姿勢は重要ですが、提示する条件を全て鵜呑みにしては不利な条件で交渉を進めることになる恐れがあります。
事前に自社の企業価値を確認しておき、その相場よりも低い条件やあまりにも不利な条件を提示された場合には取引を見直す必要があります。
早く事業承継を終わらせたい気持ちは当然あると考えられますが、理不尽な条件で交渉を終わらせると後々後悔することになります。
最後に判断するのは経営者であるご自身なので、事前に確認できることは抜けが無いようにしましょう。
競業避止義務に注意する
競業避止義務とは、M&Aを行った後に同じ地域内での就職や事業立ち上げを制限する法律になります。
買手企業が事業承継M&Aを行うことで得ることができる成果を最大化するためにも、競業避止義務を守ることが一般的に求められます。
競業避止義務には、同業他社への助言などもその範囲として含まれる可能性があるため注意が必要です。
違反した際には、損害賠償請求を受ける可能性があるので違反がないようにしましょう。
PMI(統合プロセス)を事前に構築しておく
PMIとは、「Post Merger Integration」の略で日本語では統合プロセスのことを指します。
事業承継M&Aが終了したら終わりではなく、その後に働き続ける従業員が働きやすい環境であるために、スムーズに引継ぎができるように事前に引継ぎ方法やシステムの変更等の環境整備を行うことが重要です。
今まで共に働いてきた従業員の今後のケアまで責任をもって整備すると、承継後の企業でも安心して働ける状態になります。
まとめ
事業承継型M&Aに関してや、その仕組み、事業承継型M&Aを活用する際のメリット・デメリットなどについて解説しました。
国内の中小企業は、経営者の高齢化に伴う後継者問題が露呈しており、その解決策として事業承継型M&Aを活用して同族と関係ない第三者を後継者に迎えるケースが増えています。
事業承継をM&Aを利用して行う際には、事業承継とは別にM&Aの知識も必要になります。
手続きには様々な繁雑な作業と法律の知識などが必要になるので、ご自身だけで対応するのが不安な場合には、事業承継型M&Aに詳しい専門家や知識豊富な企業コンサルタントなどに相談すると良いでしょう。



